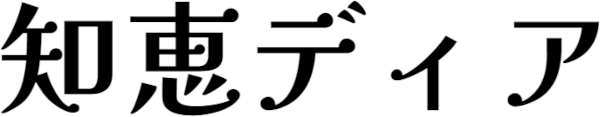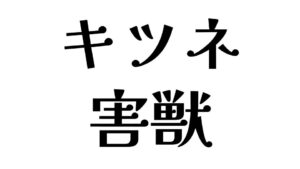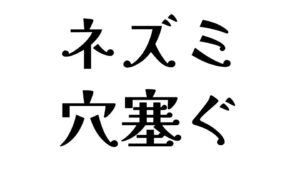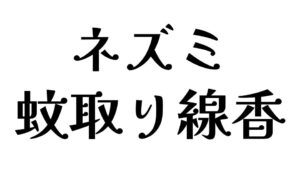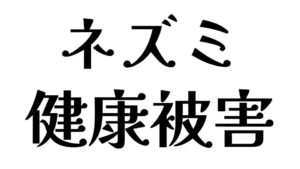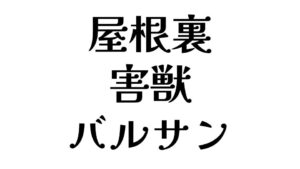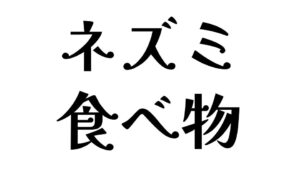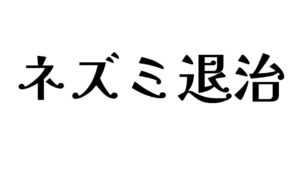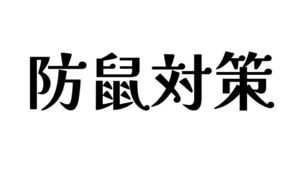アナグマはイタチ科の動物で、日本では北海道を除く本州・四国・九州に広く分布しています。目の周りに黒い縦線模様があるのが特徴で、穴掘りが得意です。温厚で警戒心が薄い性格で、人に慣れることもありますが、害獣としても知られています。アナグマはどんな被害をもたらすのでしょうか? また、アナグマを追い出すにはどうすればいいのでしょうか? 今回は、アナグマの生態と対策について解説します。
アナグマの被害とは?
アナグマは雑食性で、昆虫や小動物だけでなく、果物や野菜なども食べます。近くに食料がなくなると、人里に降りてきて農作物を食い荒らすことがあります。イチゴやスイカ、スイートコーン、落花生などの甘い農作物を好む傾向があります。養蚕施設で蚕が食べられたという報告もあります。
食害よりも深刻なのが、穴掘りによる被害です。アナグマは巣穴を地中深く掘る習性があり、床下や建物の下に巣を作ることがあります。巣穴の内部は複数の部屋に分かれており、時間が経つにつれ穴は大きくなっていきます。その結果、地盤が緩んで建物が倒壊する恐れがあります。ヨーロッパでは数百年にわたり拡大されつづけたアナグマの巨大な巣が街の下で発見された事例もあるほどです。
アナグマが住み着いてしまうと、フンを一か所にまとめて排泄する「ためフン」の習性により、フンが蓄積されて衛生状態も悪化します。感染症やアレルギーなどの健康被害につながる恐れもあります。
アナグマの対策とは?
アナグマの被害を防ぐためには、早めに対策をすることが必要です。しかし、アナグマは「鳥獣保護法」という法律で保護されており、許可なく捕獲や駆除をすることはできません。違反してしまった場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。自分で捕獲や駆除をするのではなく、追い出すことを考えましょう。以下に、アナグマを追い出す方法をいくつか紹介します。
電気柵で畑を囲う
電気柵は自分たちで追い出す方法の中で、最も高い効果が期待できます。アナグマが電気柵に触れると、感電して痛みで逃げ出します。柵が危険であるとアナグマが認識すれば、畑に寄り付かなくなり、再侵入防止にも効果的です。ただし、電気柵に雑草が触れると電圧が低くなるので、定期的に除草作業が必要になります。
忌避剤を使う
忌避剤はアナグマが嫌う臭いや味を持つもので、畑や巣穴の周りに撒いたり、スプレーしたりすることで、アナグマを遠ざけることができます。忌避剤には、ニンニクや唐辛子、石油などの天然成分のものや、化学成分のものがあります。天然成分のものは安全性が高いですが、効果が弱い場合があります。化学成分のものは効果が強いですが、人やペットにも影響を与える可能性があります。忌避剤を使う場合は、用途や成分に注意して選びましょう。
音や光で追い払う
音や光はアナグマにとって不快な刺激となり、近づきにくくなります。害獣用の対策グッズの中には、動物にとって不快となる超音波や光を出す装置があります。近づいたアナグマを追い出す効果が期待できるため、設置してみるのもよいでしょう。ただし、人やペットにも影響を与える可能性があるので、注意が必要です。
侵入経路を塞ぐ
アナグマは地面を掘って侵入することが多いので、畑や床下の周りに石や金網などで囲いを作ることで、侵入を防ぐことができます。また、アナグマが巣穴を作っている場合は、巣穴の入り口を塞いでしまうことも効果的です。ただし、巣穴にアナグマがいる場合は、閉じ込めてしまうことになるので、必ず空いていることを確認してから行いましょう。
まとめ
アナグマは可愛いけれど害獣です。農作物や建物に被害をもたらすことがあります。アナグマを追い出すには、電気柵や忌避剤、音や光、侵入経路の塞ぎなどの方法があります。しかし、アナグマは法律で保護されているので、自分で捕獲や駆除をすることはできません。もしアナグマの被害に悩んでいる場合は、プロの害獣駆除業者に相談してみるのもおすすめです。プロの害獣駆除業者は、安全性の高い駆除方法や再侵入防止の処置を行ってくれます。最新の駆除技術やノウハウを持っているので、安心して任せることができます。