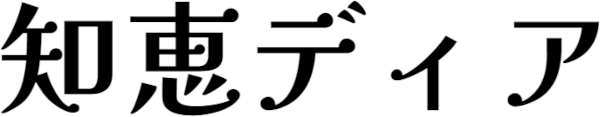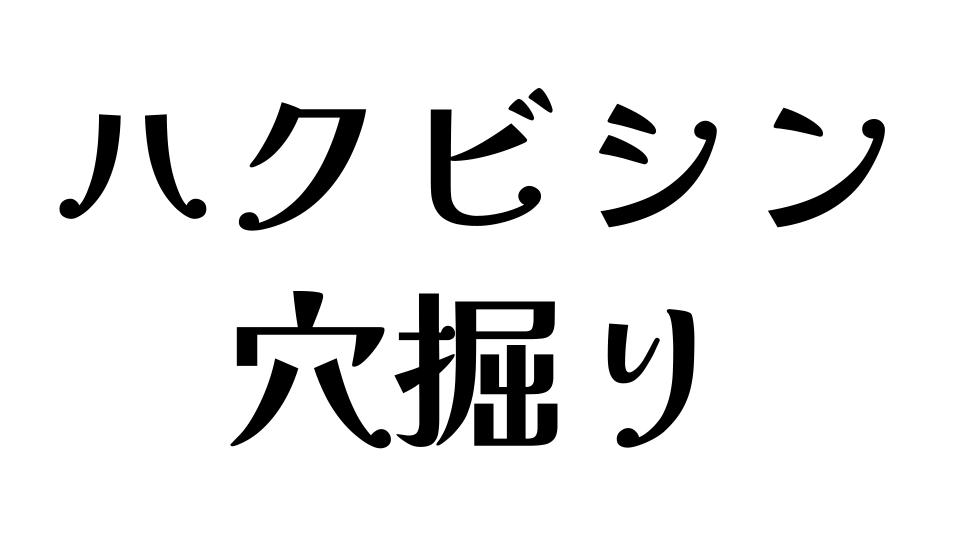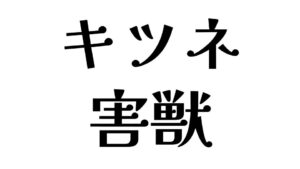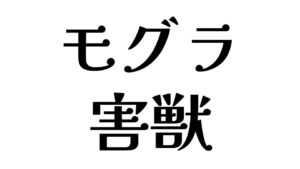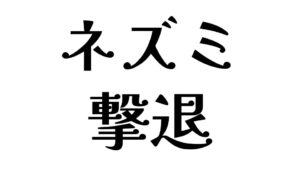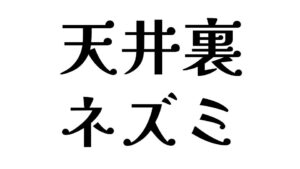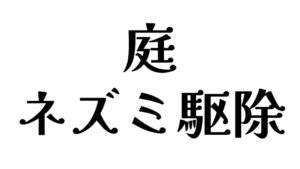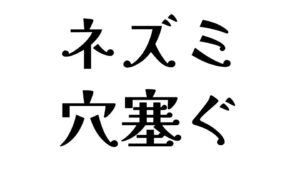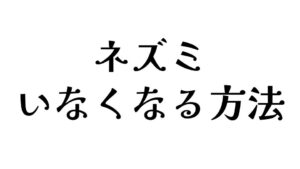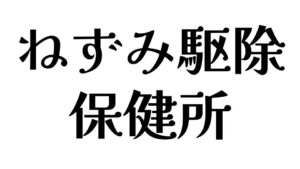ハクビシンは、日本では外来種として知られる動物です。ネコの仲間で、灰色の毛と白い顔の模様が特徴です。木登りが得意で、屋根裏や床下などに住み着いてしまうことがあります。また、雑食性で、果物や野菜、生ゴミなどを食べてしまいます。ハクビシンの被害に悩まされている方も多いのではないでしょうか?
しかし、ハクビシンは穴掘りするのでしょうか? 実は、ハクビシンは穴掘りができません。穴掘りができるのは、タヌキやアナグマなどの別の害獣です。ハクビシンは「樹の上」で生活することが多く、穴掘りをする必要がないのです。
目次
ハクビシンの特徴
では、ハクビシンと他の害獣はどうやって見分けるのでしょうか? ハクビシンの特徴は以下の通りです。
- 額から鼻の部分に白い線が入っている。
- 鼻はピンク色で、耳のふちが黒い。
- しっぽが長くてふさふさしている。
- 体長は約90~110cmで、うち40~45cmはしっぽ。
一方、タヌキやアナグマ、アライグマなどの特徴は以下の通りです⁴。
- タヌキ
- 耳は小さくて丸い。目の周りが黒くなっている。
- 鼻は黒くて大きい。耳のふちが白い。ヒゲも白くて長い。
- しっぽが短くてシマ模様がある。
- 体長は約50~60cmで、穴掘りが得意。
- アナグマ
- 耳は小さくて丸い。目の周りが黒くなっている。
- 鼻は黒くて大きい。耳のふちが白い。ヒゲも白くて長い。
- しっぽはふさふさしていない。
- 体長は約50~70cmで、穴掘りが得意。
- アライグマ
- 耳は大きくて三角形。目の周りが黒くなっている。
- 鼻は黒くて大きい。耳のふちが白い。ヒゲも白くて長い。
- しっぽが長くてシマ模様がある。
- 体長は約40~60cmで、穴掘りはできないが木登りが得意。
このように、ハクビシンと他の害獣は、見た目や体長、穴掘りや木登りの得意・不得意などで見分けることができます。畑に穴掘りの跡があったり、果物や野菜が食べられていたりする場合は、ハクビシンではなく、タヌキやアナグマなどの可能性が高いと言えます。
ハクビシンの被害を防ぐための対策
ハクビシンの被害を防ぐには、どうすればいいのでしょうか? ハクビシンは、エサになるものや隠れられる場所があれば、人間の住む場所にも侵入してきます。そのため、以下のような対策を行うことが大切です。
- 生ゴミや果物などを外に置かない。缶ジュースなどは洗って捨てる。
- 畑の野菜は柵を設けて目につかないようにする。
- 建物周辺の雑草を刈る。壁や換気口などに穴がある場合は塞ぐ。
- 屋根や畑に移動できそうな木の枝を剪定する。
- ハクビシンの天敵であるオオカミの尿などの忌避剤を使う。
- 音や光で威嚇する装置を設置する。
- 捕獲器で捕まえる。
ただし、ハクビシンは外来種であるため、捕獲した場合は、自分で放すことはできません。必ず専門の業者に依頼するか、市町村の担当部署に連絡する必要があります。また、ハクビシンは攻撃的になることもあるので、自分で触ったりしないように注意しましょう。
まとめ
ハクビシンは穴掘りはしませんが、他の害獣と間違えやすい動物です。ハクビシンの特徴や見分け方、対策方法を知って、被害を防ぐようにしましょう。