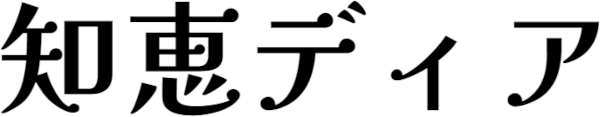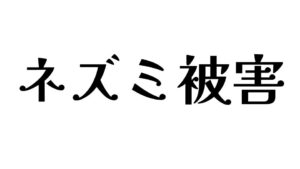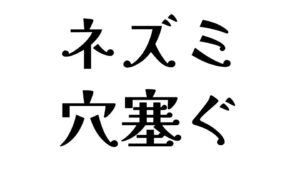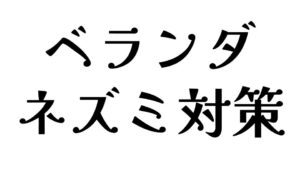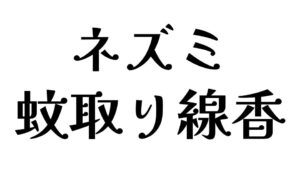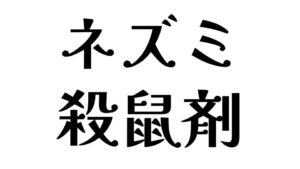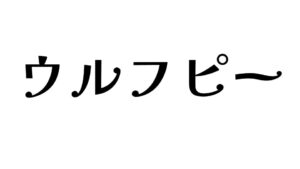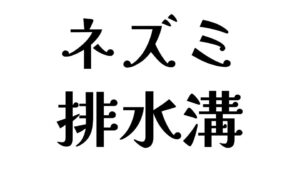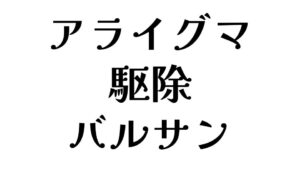猪は日本各地で農作物や森林の被害をもたらす害獣の一つです。猪の生態や習性、被害の状況や対策方法について、詳しく解説します。
猪の生態と習性
猪は雑食性で、植物や動物、キノコや根などさまざまなものを食べます。繁殖力が強く、一年に一回、4月から6月にかけて平均4~5頭の子どもを産みます。妊娠期間は約120日です。
猪は鼻がとても優れており、鼻先で50~60キロのものを持ち上げることができます。鼻で土を掘り返して食べ物を探したり、木の皮を剥いだりします。また、鼻で匂いを嗅いで仲間や敵を識別したり、縄張りを主張したりします。
猪は警戒心が強く、人間を避ける傾向がありますが、住宅地に侵入したり、刺激されると人を襲ったりすることもあります。猪は牙を持っており、攻撃されると大怪我をする危険性があります。
猪は昼間は森林に隠れており、夜間に活動することが多いです。しかし、人間の活動が少ない地域や、人間に慣れてしまった場合は、昼間にも姿を見せることがあります。猪は学習能力が高く、周囲の環境に合わせて行動を変えることができます。
猪の被害とその影響
猪は農作物や森林に大きな被害を与えます。農作物では、イネや果樹、野菜などのほとんどの作物で被害が発生します。猪は食べるだけでなく、踏みつけや掘り起こしによっても被害をもたらします。農業被害額は、2020年度で約36億円になっています¹。
森林では、猪が木の皮を剥いだり、若芽や草を食べたりすることで、樹木の成長や再生を阻害します。森林被害面積は、2020年度で約2,100ヘクタールになっています。森林の荒廃は、水源涵養や土砂災害の防止などの森林の機能を低下させるだけでなく、生物多様性の減少や地球温暖化の促進などの環境問題にもつながります。
猪の被害は、農林水産業や自然環境だけでなく、人間の生活や健康にも影響を及ぼします。猪は家庭の庭や生ゴミ置き場に侵入して荒らしたり、交通事故や人身被害を引き起こしたりすることがあります。また、猪は狂犬病や日本脳炎などの感染症の媒介者となる可能性もあります。
猪の対策とその効果
猪の被害を防止するためには、総合的な対策が必要です。具体的には、以下のような対策があります。
- 防護柵の設置:猪が農地や森林に侵入できないように、柵や塀を設置します。猪は高く跳ぶことができるので、柵の高さは1.5メートル以上にします。また、猪は下からくぐることが多いので、柵と地面の間に隙間ができないようにします。電気柵を使う場合は、猪の鼻の高さに合わせて設置し、電圧を管理します。
- 生息環境の整備:猪が隠れたり、エサを探したりする場所を減らすために、草刈りや間伐などの環境整備を行います。明るく見通しの良い環境を作ることで、猪の警戒心を高めて侵入を防ぎます。
- 捕獲による個体数の調整:猪の個体数が増えすぎたり、人間に慣れてしまったりした場合は、捕獲によって個体数を調整します。捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づいて許可を得る必要があります。捕獲した猪は、食用として利用したり、研究や教育に活用したりします。
これらの対策は、単独ではなく、地域の状況に応じて組み合わせて行うことが効果的です。また、対策を行う際には、農家や森林組合、自治体、狩猟者、専門家など、関係者が連携して情報交換や意見調整を行うことが重要です。
まとめ
猪は日本各地で農作物や森林の被害をもたらす害獣です。猪の生態や習性を知り、猪の被害とその影響を理解することが、対策の第一歩です。猪の被害を防止するためには、防護柵の設置、生息環境の整備、捕獲による個体数の調整などの総合的な対策が必要です。対策を行う際には、関係者が協力して実施することが効果的です。
猪の被害に悩む方は、ぜひ参考にしてみてください。