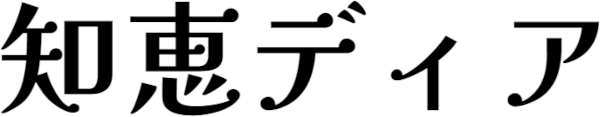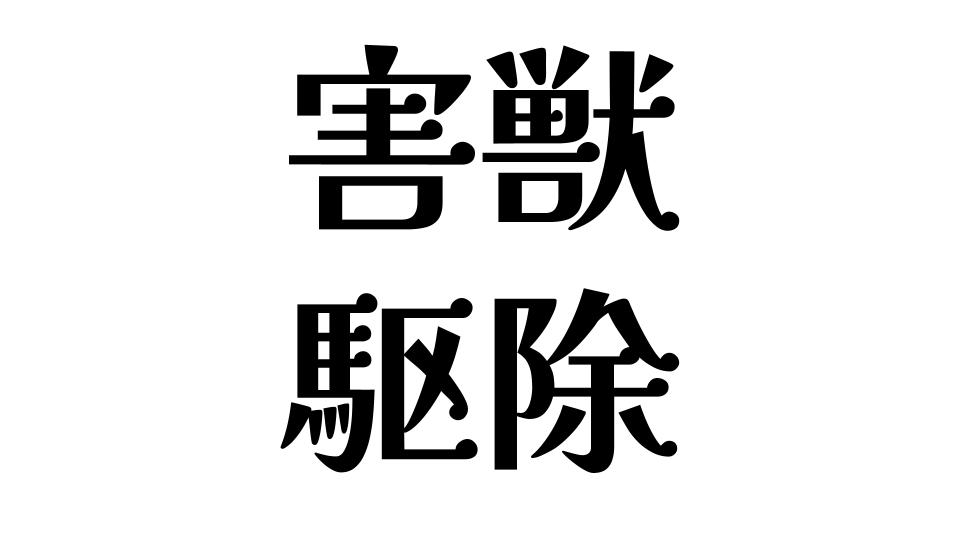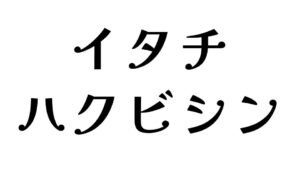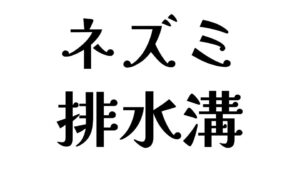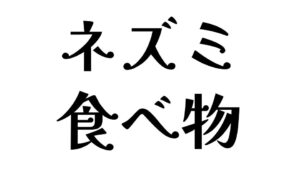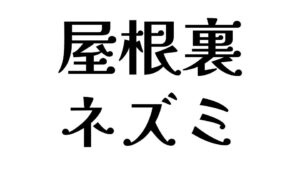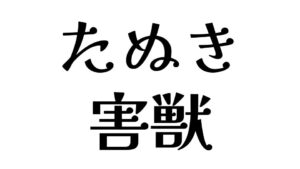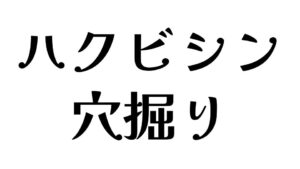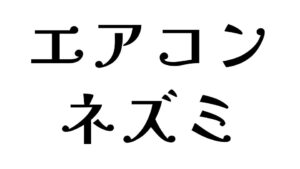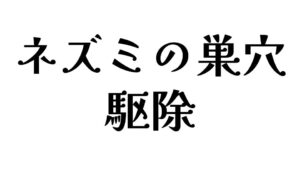家に住み着く害獣の種類はさまざまですが、その中でもイタチやハクビシン、ネズミやアライグマ、タヌキやコウモリなどが代表的です。これらの害獣は、家屋にダメージを与えたり、畑や果樹園を荒らしたり、騒音や悪臭を発生させたり、病原菌や感染症を媒介したりすることで、人間の生活に大きな被害をもたらします。
そこで、この記事では、家に住み着く害獣の種類や特徴、被害の内容、そして駆除する方法について詳しく解説します。害獣に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
害獣を駆除するには法律を守る必要がある
害獣を駆除するには、法律を守る必要があります。日本では、鳥獣の保護や管理、狩猟の適正化に関する法律である「鳥獣保護管理法」と、外来生物の導入や放出を規制する法律である「外来生物法」があります。
鳥獣保護管理法では、鳥獣や鳥獣の卵の捕獲、殺傷、採取、損傷させることを原則として禁止しています。ただし、例外として、行政から許可を受けての捕獲や、一定の条件下での狩猟が認められています。
外来生物法では、国内の自然の生態系を守るために、在来種ではない生き物を許可なく捕獲・輸入することを禁止しています。特に、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすものを「特定外来生物」として指定し、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、放出、譲渡しを厳しく規制しています。
害獣を自力で捕獲する場合は、これらの法律に従って、必要な許可や手続きを行う必要があります。また、捕獲した害獣の処分や再発防止の対策も適切に行わなければなりません。法律に違反すると、罰金や懲役などの刑事罰が科せられる可能性がありますので、注意してください。
害獣の種類と特徴、被害の内容
ここからは、家に住み着く可能性のある害獣の種類と特徴、被害の内容について、それぞれご紹介します。害獣の存在に気づいたら、早めに対処しましょう。
イタチ
イタチは、屋根裏に潜んでいることが多い害獣です。その可愛らしい外見とは裏腹に、非常に凶暴で、自分よりも大きなウサギやニワトリも捕食します。また、泳ぎが得意なので、海岸部や河川沿いの家屋が被害を受けやすいという特徴があります。
イタチによる被害の中でとくに困るのは、発達した肛門腺から噴出する分泌液です。この分泌液は外敵から身を守るために噴出するもので、非常に強い臭いを放ちます。イタチの分泌液は、人間の目や鼻、皮膚に刺激を与えるだけでなく、アレルギー反応を引き起こすこともあります。
イタチの駆除方法としては、捕獲器を使って捕獲する方法があります。捕獲器は、自治体から借りることができますが、捕獲許可が必要です。また、イタチは警戒心が強いので、捕獲器の設置場所や餌の選び方に工夫が必要です。
ハクビシン
ハクビシンは、鼻に白い筋があるレッサーパンダに似た可愛らしい外見をしています。しかし、ハクビシンは畑や果樹園を荒らしたり、家屋に被害をもたらしたりする危険な害獣です。また、ハクビシンの体についているマダニから「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」という感染症にかかるリスクもあります。
そんなハクビシンには、糞をする場所を決めるとずっとそこに排泄し続ける「ため糞」という厄介な習性があります。ハクビシンは警戒心が強く、屋根裏に住み着くことが多いので、屋根裏に排泄され続けてしまうことで天井が腐食して抜けてしまったり、悪臭やダニの繁殖といった二次被害が発生したりするので注意が必要です。
ハクビシンの駆除方法としては、イタチと同様に捕獲器を使って捕獲する方法があります。捕獲器は、自治体から借りることができますが、捕獲許可が必要です。また、ハクビシンは特定外来生物に指定されているので、外来生物法に基づく防除の確認・認定を受ける必要があります。
ネズミ
害獣の代表格ともいえるネズミは、家屋や店舗の屋根裏に住み着いて、電線や断熱材をかじったり、糞尿を撒き散らしたりします。また、ネズミは病原菌や寄生虫を媒介することで、人間に感染症を引き起こす可能性があります。
ネズミの駆除方法としては、ネズミ捕りや毒餌を使って捕獲する方法があります。ネズミ捕りは、スナップ式や粘着式などの種類がありますが、どちらもネズミの通り道に設置しておくことで、ネズミを捕まえることができます。毒餌は、ネズミが食べると出血や中毒などで死ぬように作られた餌で、ネズミの巣穴や隠れ場所に置いておくことで、ネズミを駆除することができます。
アライグマ
アライグマは、顔に黒いマスクのような模様がある可愛らしい外見をしていますが、実は非常に強力な前足と鋭い爪を持ち、家屋の壁や屋根を破壊したり、ゴミ箱を荒らしたりする害獣です。また、アライグマは狂犬病や回虫などの病気を媒介することで、人間やペットに感染させる危険性があります。
アライグマの駆除方法としては、ハクビシンと同様に捕獲器を使って捕獲する方法があります。捕獲器は、自治体から借りることができますが、捕獲許可が必要です。また、アライグマも特定外来生物に指定されているので、外来生物法に基づく防除の確認・認定を受ける必要があります。
タヌキ
タヌキは、日本の伝統的な動物として親しまれていますが、実は家屋や農作物に被害を与える害獣です。タヌキは、屋根裏や床下に巣を作ったり、畑や果樹園を荒らしたり、ゴミ箱を漁ったりします。また、タヌキは狂犬病やエキノコックスなどの病気を媒介することで、人間やペットに感染させる危険性があります。
タヌキの駆除方法としては、捕獲器を使って捕獲する方法があります。捕獲器は、自治体から借りることができますが、捕獲許可が必要です。また、タヌキは鳥獣保護管理法に基づく「特別捕獲対象鳥獣」に指定されているので、捕獲後は速やかに殺処分するか、適切な場所に放獣する必要があります。
コウモリ
コウモリは、夜行性の動物で、昼間は屋根裏や壁の隙間に隠れています。コウモリは、糞尿や死骸を撒き散らすことで、天井や壁を汚したり、悪臭やダニの繁殖を引き起こしたりします。また、コウモリは狂犬病やヘンドラウイルスなどの病気を媒介することで、人間やペットに感染させる危険性があります。
コウモリの駆除方法としては、コウモリが出入りする穴を塞ぐ方法や、コウモリが嫌う音や光を発する装置を設置する方法があります。コウモリは鳥獣保護管理法に基づく「特別捕獲対象鳥獣」に指定されているので、捕獲器や毒餌を使って捕獲することは禁止されています。
害獣駆除のプロに依頼するメリット
害獣駆除は、自力で行うこともできますが、法律や手続きに詳しくないと、違反してしまう可能性があります。また、害獣は非常に用心深く、捕獲器や毒餌に気づいて回避することもあります。さらに、害獣に触れると、噛まれたり引っかかれたりする危険性や、病気に感染するリスクもあります。
そこで、害獣駆除のプロに依頼するメリットを紹介します。
- 法律や手続きに精通しているので、違反やトラブルを防ぐことができます。
- 害獣の習性や生態に詳しく、効果的な駆除方法を選択してくれます。
- 害獣の捕獲や処分を代行してくれるので、危険や不快感を感じることがありません。
- 害獣の巣や糞尿などの清掃や消毒を行ってくれるので、二次被害を防ぐことができます。
- 害獣の侵入経路や原因を特定してくれるので、再発防止の対策を提案してくれます。
害獣駆除のプロに依頼する場合は、インターネットや電話で相談や見積もりを依頼することができます。害獣駆除の費用は、害獣の種類や被害の程度、駆除方法や対策内容によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度です。
まとめ
家に住み着く害獣の種類や特徴、被害の内容、そして駆除する方法について詳しく解説しました。害獣に悩んでいる方は、早めに対処しましょう。自力で駆除する場合は、法律や手続きに注意してください。プロに依頼する場合は、インターネットや電話で相談や見積もりを依頼することができます。
家に住み着く害獣は、人間の生活に大きな被害をもたらします。害獣に気づいたら、早めに対処しましょう。害獣駆除の方法は、自力で行う方法とプロに依頼する方法がありますが、どちらも法律や手続きに注意する必要があります。自力で駆除する場合は、捕獲器や毒餌などを使って害獣を捕獲することができますが、危険や不快感を感じることもあります。プロに依頼する場合は、法律や手続きに精通した専門家が害獣の捕獲や処分、清掃や消毒、再発防止の対策を行ってくれますが、費用がかかることもあります。自分の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。