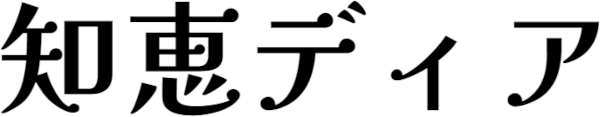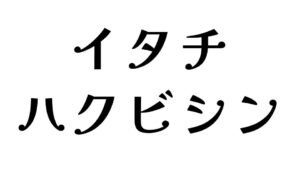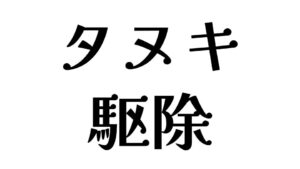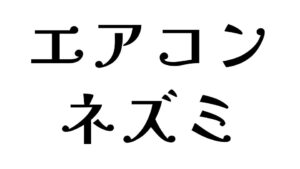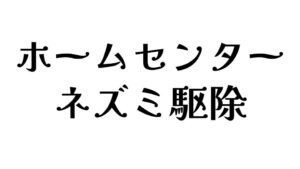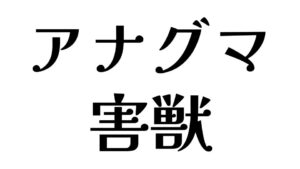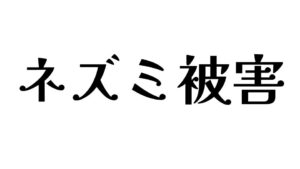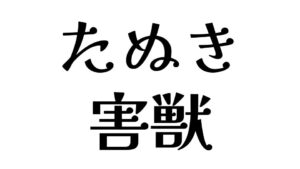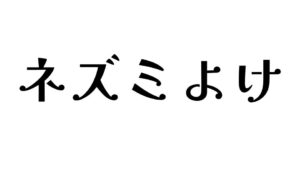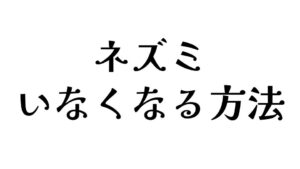動物が家に侵入したり、畑や果樹園を荒らしたりすると、人間の生活に大きな被害をもたらします。そんなときには、動物を駆除する必要がありますが、どのように対処すれば良いのでしょうか。
この記事では、動物駆除について以下のことを解説します。
- 動物駆除とは何か
- 駆除の方法と注意点
- 動物駆除に関する法律と制度
- 駆除の代わりにできる予防策
動物駆除とは何か
動物駆除とは、人間の生活に害をもたらす動物を捕獲したり、殺処分したりすることを指します。日本では、イタチ、ハクビシン、ネズミ、アライグマ、タヌキ、コウモリなどが代表的な害獣として知られています¹²。
害獣による被害は、以下のようなものがあります。
- 家屋や建物にダメージを与える
- 畑や果樹園を荒らす
- 騒音や悪臭を発生させる
- 病原菌や感染症を媒介する
- 家畜やペットを襲う
これらの被害を防ぐためには、害獣を駆除する必要がありますが、駆除する際には法律やルールに従わなければなりません。
駆除の方法と注意点
駆除の方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 自力で駆除する
- 業者に依頼する
- 市町村に相談する
自力で駆除する場合は、鳥獣保護管理法に基づいた「捕獲許可」が必要になります³。捕獲許可は、市町村の農林水産課などに申請することで取得できますが、捕獲する動物や方法、期間、場所などが限定されます。また、捕獲した動物は、殺処分するか、市町村の職員に引き渡す必要があります。
業者に依頼する場合は、鳥獣捕獲の事業の認定を受けた業者に依頼することが望ましいです。認定業者は、鳥獣保護管理法の規定に従って駆除を行うことができます。駆除の費用は、業者によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度が相場です。
市町村に相談する場合は、市町村が害獣の駆除を行ってくれる場合があります。市町村によっては、駆除の費用を一部負担してくれる場合もあります。ただし、市町村が駆除を行ってくれるのは、害獣による被害が深刻な場合や、駆除が困難な場合に限られます。
駆除を行う際には、以下の点に注意する必要があります。
- 駆除する動物によっては、外来生物法に基づく規制がかかる場合がある。例えば、アライグマは特定外来生物に指定されており、飼育や輸入、放出、譲渡などが禁止されています。
- 駆除する動物によっては、狩猟法に基づく規制がかかる場合がある。例えば、タヌキは狩猟鳥獣に指定されており、狩猟期間や狩猟方法に制限があります。
- 駆除する動物によっては、動物愛護法に基づく規制がかかる場合がある。例えば、コウモリは絶滅危惧種に指定されており、殺処分することは原則として禁止されています。
動物駆除に関する法律と制度
動物駆除に関する法律と制度は、以下のようなものがあります。
- 鳥獣保護管理法:鳥類や哺乳類の保護と管理、狩猟の適正化に関する法律³。
- 外来生物法:国内の自然の生態系を守るために、在来種ではない生き物を許可なく捕獲・輸入することを規制する法律。
- 狩猟法:狩猟の許可や禁止、狩猟鳥獣の指定や狩猟期間の設定などに関する法律。
- 動物愛護法:動物の命や健康を守るために、殺処分や虐待などを規制する法律。
- 鳥獣捕獲の事業の認定制度:鳥獣の捕獲を事業として行う者に対して、鳥獣保護管理法に基づいて認定を行う制度。
- 鳥獣被害防止対策費交付制度:鳥獣による被害を防止するために、国が市町村に対して費用を交付する制度。
駆除の代わりにできる予防策
駆除は、法律やルールに従って行わなければならない上に、動物の命を奪うことになります。そのため、できるだけ駆除を避けるために、予防策をとることが望ましいです。
駆除の代わりにできる予防策は、以下のようなものがあります。
- 家の周りにフェンスやネットを張る
- 屋根裏や床下に侵入口を作らないようにする
- 食べ物やゴミを外に放置しない
- 防虫剤や忌避剤を使う
- 鳴き声や音楽などで動物を威嚇する
- 動物に餌を与えない
これらの予防策は、動物が人間の生活圏に近づくことを防ぐことができます。また、動物に対して優しく接することも大切です。動物は、人間に脅かされたり、攻撃されたりすると、逆に反撃したり、縄張り意識を強めたりすることがあります。
まとめ
動物駆除は、人間の生活に害をもたらす動物を捕獲したり、殺処分したりすることです。しかし、駆除する際には、法律やルールに従わなければなりません。また、駆除は動物の命を奪うことになるので、できるだけ予防策をとることが望ましいです。