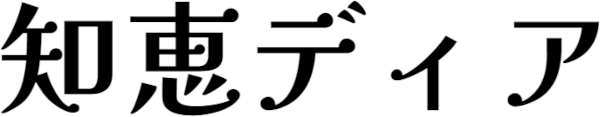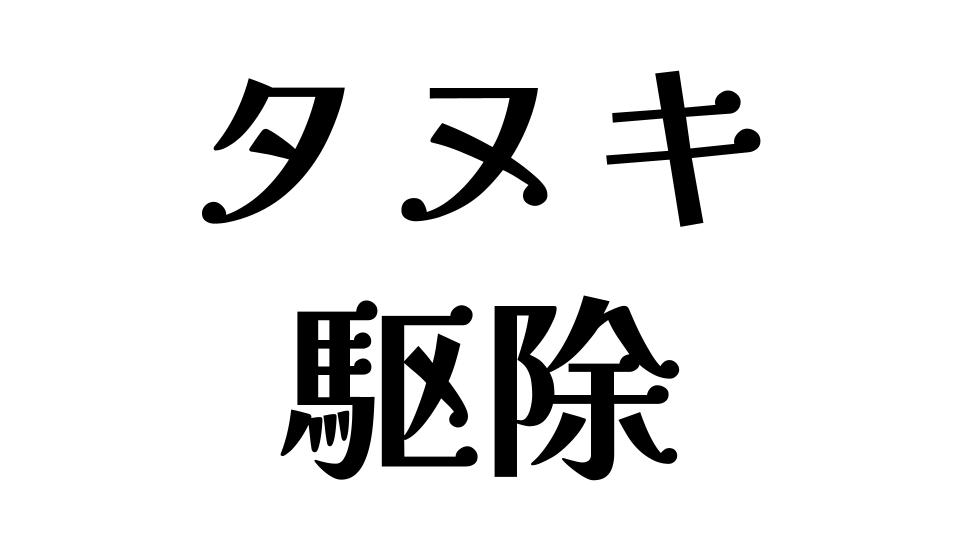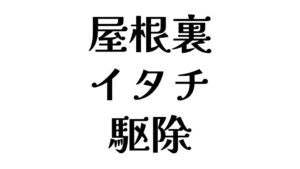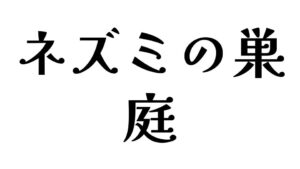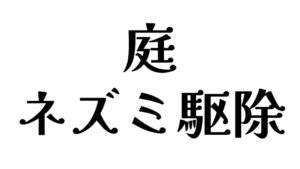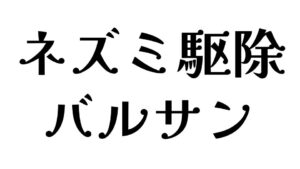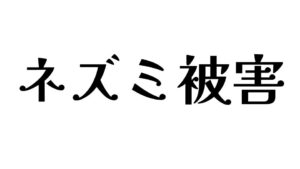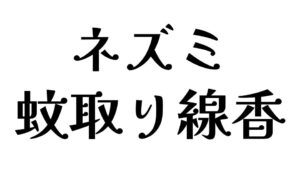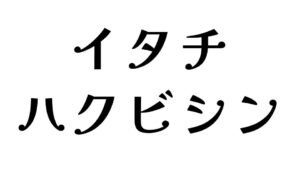タヌキは日本全国に生息するイヌ科の動物ですが、害獣として農作物や家屋に被害を与えることがあります。タヌキは鳥獣保護管理法で保護されているため、許可なく駆除や捕獲することはできません。しかし、被害が深刻な場合は、市役所に申請して駆除の許可を取ることができます。また、自分でできる追い出しや侵入防止の対策もあります。この記事では、タヌキの駆除方法と予防策について詳しく解説します。
タヌキの駆除方法
タヌキの駆除方法は大きく分けて、市役所や業者に依頼する方法と、自分で行う方法があります。市役所や業者に依頼する場合は、確実に駆除できますが、費用がかかることが多いです。自分で行う場合は、費用を抑えることができますが、法律や安全に注意する必要があります。
市役所や業者に依頼する方法
市役所や業者に依頼する場合は、以下の手順で行います。
- 市役所に駆除の許可を申請する
- 市役所から駆除の許可が下りるのを待つ
- 市役所や業者に駆除を依頼する
- 駆除が完了するのを確認する
市役所に駆除の許可を申請する際には、「鳥獣の捕獲等許可申請書」を提出する必要があります。申請に必要な書類や方法は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。駆除の許可が下りるまでには、数日から数週間かかることがあります。駆除の許可が下りたら、市役所や業者に駆除を依頼します。市役所の場合は、無料で駆除してくれることもありますが、業者の場合は、駆除にかかる費用を見積もってもらいましょう。駆除が完了したら、市役所に駆除の報告をする必要があります。
自分で行う方法
自分で行う方法は、以下のようなものがあります。
- タヌキの苦手なにおいで追い出す
- タヌキの侵入を防ぐ
- タヌキの糞を掃除して消毒する
タヌキの苦手なにおいで追い出す方法は、市販の忌避剤や木酢液、ミントなどを使う方法です。タヌキはこれらの強いにおいを嫌うため、被害のある場所に撒いたり、設置したりすることで追い出すことができます。ただし、雨で流れてしまったり、においが薄れてしまったりすることがあるため、定期的に散布や交換をする必要があります。
タヌキの侵入を防ぐ方法は、フェンスやネット、金網などで侵入口を塞ぐ方法です。タヌキは7.5cmほどの隙間や穴があれば侵入できるため、網目の大きさが7.5cmよりも小さいものを選びましょう。また、タヌキは木登りができるため、フェンスの上部にもネットや金網を張るとより効果的です。
タヌキの糞を掃除して消毒する方法は、タヌキが再び同じ場所に戻ってこないようにする方法です。タヌキは常に同じ場所で糞をする習性があり、においが残っていると戻ってくることがあります。そのため、タヌキの糞を見つけたら、すぐに掃除して消毒しましょう。タヌキの糞には感染症の原因となる細菌が含まれている可能性があるため、掃除するときは長袖長ズボン、軍手を着用し、肌の露出を避けましょう。また、作業後には必ず手洗いと消毒をしましょう。
タヌキの予防策を知ろう!
タヌキの駆除方法を知ったところで、最後にタヌキの予防策について紹介します。タヌキは餌や隠れ場所を求めて人間の住む場所に近づいてきます。そのため、タヌキを寄せ付けないためには、以下のことに注意しましょう。
- 餌となるものをなくす
- 隠れられる場所をなくす
餌となるものをなくす方法は、タヌキが好む野菜や果物、ペットフードなどを置かないようにする方法です。タヌキは雑食で何でも食べますが、とくに糖度の高いものを好みます。そのため、庭や畑に野菜や果物を育てている場合は、収穫時期には早めに収穫しましょう。また、ペットフードやゴミ袋などは屋内にしまっておきましょう。
隠れられる場所をなくす方法は、タヌキが寝床にする屋根裏や床下、倉庫などの隙間や穴を塞ぐ方法です。タヌキは屋根裏や床下などに住み着いてしまうと、フン尿や騒音などの被害をもたらします。そのため、タヌキが侵入できないように、隙間や穴をワイヤーメッシュやネット、金網などで塞ぎましょう。また、庭や畑には草や枝などの隠れ場所をなくしましょう。
まとめ
タヌキの駆除方法と予防策について詳しく解説しました。タヌキは鳥獣保護管理法で保護されているため、許可なく駆除や捕獲することはできません。しかし、被害が深刻な場合は、市役所に申請して駆除の許可を取ることができます。また、自分でできる追い出しや侵入防止の対策もあります。タヌキを寄せ付けないためには、餌となるものをなくす、隠れられる場所をなくすなどの予防策をとりましょう。タヌキとの共存のためにも、法律や安全に注意しながら、適切な対処をしましょう。