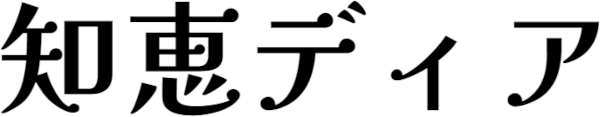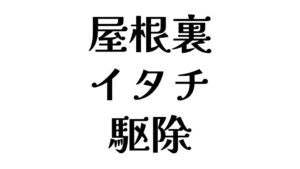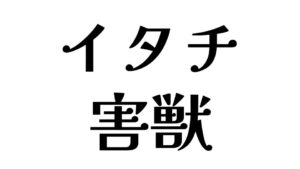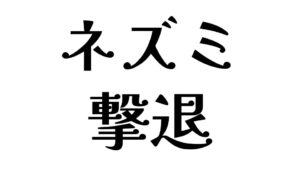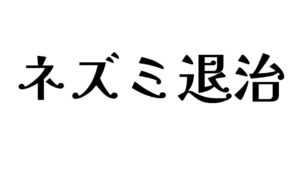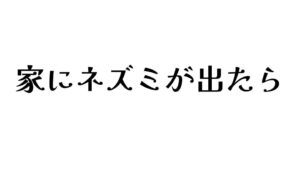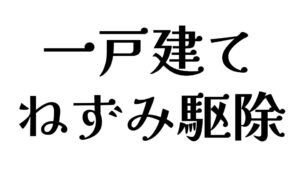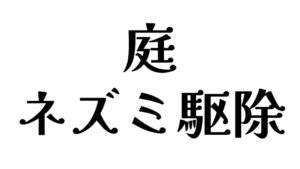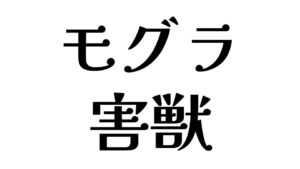害獣とは、人間の生活に被害を与える野生動物のことです。アライグマやハクビシン、イタチなどが代表的な害獣ですが、ネズミやハトなども害獣に含まれます。害獣は、屋根裏や床下などに侵入して騒音や臭いを発生させたり、家屋や農作物を破壊したり、感染症を媒介したりすることがあります。そのため、害獣が発生した場合は、早急に対策をする必要があります。
しかし、害獣駆除には法律やルールがあり、自分で勝手に行うことはできません。害獣のほとんどは、鳥獣保護管理法によって保護されており、許可なく駆除や捕獲をすると、罰金や懲役の対象になることがあります。そのため、害獣駆除を自分で行う場合は、正しい方法と注意点を知っておく必要があります。
この記事では、自分でできる害獣駆除の方法と注意点について、以下の順にご紹介します。
- 自分で駆除できる害獣とできない害獣
- 自分で駆除できる害獣の対処法
- 捕獲器を使う方法
- 忌避剤を使う方法
- 自分で駆除できない害獣の対処法
- 業者に依頼する方法
- 自治体に相談する方法
- 害獣駆除の再発防止策
自分で駆除できる害獣とできない害獣
まず、自分で駆除できる害獣とできない害獣について説明します。鳥獣保護管理法では、鳥類や哺乳類に属する野生動物は、一部の例外を除いて、許可なく駆除や捕獲をすることが禁止されています。例外となるのは、以下のような害獣です。
- ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなど)
- 海棲哺乳類(アザラシ、オットセイなど)
- その他の特定の害獣(ハト、カラス、イノシシ、シカなど)
これらの害獣は、自分で駆除することが可能ですが、それでもなるべく専門の業者に依頼することをおすすめします。なぜなら、害獣は感染症や怪我の危険があるため、自分で対処するときは十分な注意が必要だからです。また、駆除した後の処分や清掃、消毒などの作業も必要ですが、これらの作業は業者に任せることができます。
一方、以下のような害獣は、自分で駆除することができません。
- アライグマ
- ハクビシン
- イタチ
- モグラ
- リス
- タヌキ
- キツネ
- ネコ
これらの害獣は、鳥獣保護管理法で保護されているため、許可なく駆除や捕獲をすると、罰則の対象になります。そのため、これらの害獣が発生した場合は、自分で駆除することはできません。しかし、自治体に申請をして許可を得れば、捕獲器を借りて自分で捕獲することができます。また、忌避剤を使って追い出すこともできます。もしくは、業者に依頼して駆除してもらうこともできます。
自分で駆除できる害獣の対処法
次に、自分で駆除できる害獣の対処法について見ていきます。自分で駆除できる害獣の対処法は、主に以下の2つです。
- 捕獲器を使う方法
- 忌避剤を使う方法
捕獲器を使う方法
捕獲器を使う方法は、害獣を生け捕りにする方法です。市販の捕獲器を購入して設置するか、自作することができます。捕獲器の種類には、以下のようなものがあります。
- ワナ型:害獣が餌に近づくと、扉が閉まって閉じ込めるタイプの捕獲器です。害獣に怪我をさせないために、鋭利な部分がないか確認しましょう。
- 網型:害獣が餌に近づくと、網が落ちて覆うタイプの捕獲器です。害獣が網から逃げ出さないように、重しを置いたり、網の端を固定したりしましょう。
- 粘着型:害獣が餌に近づくと、粘着シートに足をくっつけて動けなくなるタイプの捕獲器です。害獣に苦痛を与えないために、粘着力が強すぎないものを選びましょう。
捕獲器を設置するときのポイントは、以下のようなものがあります。
- 害獣の侵入経路や被害のある場所に設置する
- 害獣が好む餌を捕獲器の中に置く
- 捕獲器や餌を設置するときには手袋をする
- 捕獲器を毎日確認し、捕獲したらすぐに処分する
捕獲器を使う方法のメリットは、害獣を確実に捕まえることができることです。デメリットは、捕獲器の購入や設置に手間がかかることや、以下のようなものがあります。
- 捕獲した害獣の処分や清掃に困ることがある
- 捕獲器が人間やペットに誤って作動する危険がある
- 捕獲器が害獣に破壊されたり、盗まれたりする可能性がある
捕獲した害獣の処分方法は、以下のようなものがあります。
- 殺処分:害獣を殺す方法です。殺処分には、首を絞める、頭を叩く、毒を飲ませるなどの方法がありますが、いずれも害獣に苦痛を与えることになります。また、殺処分した後の死骸の処理や消毒も必要です。そのため、殺処分はできるだけ避けるべきです。
- 野放し:害獣を捕獲した場所から離れた場所に放す方法です。野放しには、害獣を自然に帰す、動物園や保護施設に引き取ってもらうなどの方法があります。しかし、野放しには、以下のような問題があります。
- 害獣が元の場所に戻ってくる可能性がある
- 害獣が他の場所で被害を起こす可能性がある
- 害獣が移動中に事故に遭う可能性がある
- 害獣が新しい環境に適応できない可能性がある
- 害獣が他の動物との競合や感染症の拡散を引き起こす可能性がある
- 動物園や保護施設が害獣を受け入れてくれない可能性がある
そのため、野放しは、害獣の生態系や環境への影響を考慮して、慎重に行う必要があります。
捕獲した害獣の処分に困った場合は、以下のような方法があります。
- 業者に依頼する:害獣駆除の専門業者に依頼して、捕獲した害獣の処分や清掃をしてもらう方法です。業者に依頼すると、害獣の処分や清掃にかかる手間や費用がかかりますが、安全かつ適切に対処してもらえます。
- 自治体に相談する:害獣の発生が多い場合や、害獣の処分に困った場合は、住んでいる地域の自治体に相談する方法です。自治体に相談すると、害獣の処分や清掃の方法や費用、補助金などの情報を教えてもらえます。また、自治体によっては、害獣の処分や清掃を行ってくれる場合もあります。
忌避剤を使う方法
忌避剤を使う方法は、害獣を追い払う方法です。市販の忌避剤を購入して使用するか、自作することができます。忌避剤の種類には、以下のようなものがあります。
- 臭い型:害獣が嫌う臭いを発する忌避剤です。タバスコやニンニク、石鹸などが代表的な臭い型の忌避剤です。臭い型の忌避剤は、害獣の侵入経路や被害のある場所に置くか、スプレーすることで使用できます。
- 音型:害獣が嫌う音を発する忌避剤です。超音波やサイレン、鈴などが代表的な音型の忌避剤です。音型の忌避剤は、害獣の侵入経路や被害のある場所に設置することで使用できます。
- 光型:害獣が嫌う光を発する忌避剤です。フラッシュライトや反射板、ミラーボールなどが代表的な光型の忌避剤です。光型の忌避剤は、害獣の侵入経路や被害のある場所に設置することで使用できます。
忌避剤を使用するときのポイントは、以下のようなものがあります。
- 害獣の種類や習性に合わせて忌避剤を選ぶ
- 忌避剤の効果が持続するように定期的に交換や補充をする
- 忌避剤の使用によって人間やペットに影響がないか確認する
- 忌避剤の使用によって害獣が別の場所に移動しないか注意する
忌避剤を使う方法のメリットは、害獣を殺さずに追い払うことができることです。デメリットは、害獣が忌避剤に慣れてしまう可能性があることや、忌避剤の効果が十分でない場合があることです。
自分で駆除できない害獣の対処法
最後に、自分で駆除できない害獣の対処法について見ていきます。自分で駆除できない害獣の対処法は、主に以下の2つです。
- 業者に依頼する方法
- 自治体に相談する方法
業者に依頼する方法
業者に依頼する方法は、害獣駆除の専門業者に依頼して、害獣の駆除や捕獲をしてもらう方法です。業者に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 害獣の種類や習性に応じた適切な駆除方法を選んでくれる
- 害獣の駆除や捕獲に必要な許可や手続きを代行してくれる
- 害獣の駆除や捕獲に必要な器具や薬品を用意してくれる
- 害獣の駆除や捕獲に伴うリスクやトラブルを回避してくれる
- 害獣の駆除や捕獲後の処分や清掃を行ってくれる
業者に依頼するときのポイントは、以下のようなものがあります。
- 害獣駆除の専門資格や経験を持った業者を選ぶ
- 業者の評判や口コミを確認する
- 業者の料金やサービス内容を明確に確認する
- 業者との契約内容や保証内容を書面で交わす
自治体に相談する方法
自治体に相談する方法は、住んでいる地域の自治体に相談して、害獣の駆除や捕獲の方法や支援を教えてもらう方法です。自治体に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 害獣の駆除や捕獲に必要な許可や手続きの方法を教えてもらえる
- 害獣の駆除や捕獲に必要な器具や薬品を貸してもらえる
- 害獣の駆除や捕獲に関する情報やアドバイスを教えてもらえる
- 害獣の駆除や捕獲に関する費用や補助金の制度を教えてもらえる
- 害獣の駆除や捕獲に関する業者の紹介や斡旋をしてもらえる
自治体に相談するときのポイントは、以下のようなものがあります。
- 害獣の種類や被害の状況を詳しく説明する
- 自治体の担当部署や窓口を確認する
- 自治体の対応時間や対応範囲を確認する
- 自治体の指示やルールに従う
害獣駆除の再発防止策
害獣駆除の後には、再発防止策を行うことが重要です。再発防止策には、以下のようなものがあります。
- 害獣の侵入経路や隠れ場所をふさぐ
- 害獣の餌となる食べ物やゴミを片付ける
- 害獣の糞や尿などの痕跡を消毒する
- 忌避剤や防護ネットなどを設置する
- 害獣の発生や被害の状況を定期的に確認する
まとめ
害獣駆除は、人間と動物の共存のために必要なことですが、同時に動物の命や環境に配慮することも大切です。害獣駆除を行うときは、法律やルールを守り、安全かつ適切な方法を選びましょう。また、害獣駆除の専門家や自治体に相談することも、効果的な害獣駆除に役立ちます。